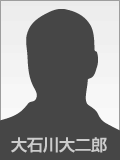ラップ理論を駆使 丹下日出夫の予想
丹下日出夫の見解
いいね!
138
【圧倒】舞台は京都、中央の高速ダートならマテラスカイ。本年春は、1000万・準オープンを連勝して、ドバイ・ゴールデンシャヒーンにアタック。スピード自慢が揃う世界のダートGI勢を相手に、巧みにインを立ち回り、見る者の腰を一瞬浮かす、あわやのシーンを演出してみせた(結果5着)。帰国初戦の花のみちSは1分10秒7、後続をチギる一方の楽勝。続くプロキオンSも、1000m通過・56秒3-1200m通過1分7秒5という超Hペースを自らが演出し、2着に0秒7の圧勝。
今夏の中京ダートは時計が速く、不良馬場というアシストを得たとはいえ、従来のコースレコードを1秒6も更新する、1分20秒3のレコードと健脚ぶりには瞠目だ。東京盃は久々、18キロ増。ハナに立つまでに少し脚を使い、残り100mあたりでアゴが上がってしまったが、木曜追い切りは50秒3。本番仕様に気合を注入した。
逆転があればレッツゴードンキ。ダートはJBCレディスクラシック(川崎1600m)が2着、今年のフェブラリーSが6着。芝同様、なかなか勝ち切れないけれど、芝・ダートを問わず、ベストは1200m。ふたを開けたら京都6Fダートが最も適していたという可能性だって高い。
キタサンミカヅキは東京盃で中央勢を一蹴。四肢が張り立ち姿は極上、触れれば弾ける鉄紺の皮膚。中央で一度限界がきたが、その当時をはるかに上回る、京都の時計勝負でも期待したくなる身体造りができている。
東京盃僅差3着のグレイトリープも小差。モーニンも唸るようなデキ。ネロ、セイウンコウセイなど、連下は手広く丁寧に。
今夏の中京ダートは時計が速く、不良馬場というアシストを得たとはいえ、従来のコースレコードを1秒6も更新する、1分20秒3のレコードと健脚ぶりには瞠目だ。東京盃は久々、18キロ増。ハナに立つまでに少し脚を使い、残り100mあたりでアゴが上がってしまったが、木曜追い切りは50秒3。本番仕様に気合を注入した。
逆転があればレッツゴードンキ。ダートはJBCレディスクラシック(川崎1600m)が2着、今年のフェブラリーSが6着。芝同様、なかなか勝ち切れないけれど、芝・ダートを問わず、ベストは1200m。ふたを開けたら京都6Fダートが最も適していたという可能性だって高い。
キタサンミカヅキは東京盃で中央勢を一蹴。四肢が張り立ち姿は極上、触れれば弾ける鉄紺の皮膚。中央で一度限界がきたが、その当時をはるかに上回る、京都の時計勝負でも期待したくなる身体造りができている。
東京盃僅差3着のグレイトリープも小差。モーニンも唸るようなデキ。ネロ、セイウンコウセイなど、連下は手広く丁寧に。
至高の頭脳 須田鷹雄の予想
須田鷹雄の見解
いいね!
514
徹底データ分析 コンピューター予想の予想
コンピューター予想の見解
いいね!
0
各馬の上昇度・脚質・騎手・調教師・血統データを「先週最も儲かった」設定で解析。導き出された4頭の馬単・3連単ボックスで勝負!
なお、プレミアムサービス(※)にご登録されますと、中央競馬全レースで、上昇度・脚質・騎手・調教師・血統の項目を自由にカスタマイズして予想することができます。各レース情報ページの予想タブから「CP予想」にお進みいただき、ご利用ください。
※netkeiba.comのスマートフォン版・競馬総合チャンネルでは、プレミアムコースにご登録されますとご利用頂けます。
なお、プレミアムサービス(※)にご登録されますと、中央競馬全レースで、上昇度・脚質・騎手・調教師・血統の項目を自由にカスタマイズして予想することができます。各レース情報ページの予想タブから「CP予想」にお進みいただき、ご利用ください。
※netkeiba.comのスマートフォン版・競馬総合チャンネルでは、プレミアムコースにご登録されますとご利用頂けます。
高配当もズバリ! netkeiba関西本紙の予想
netkeiba関西本紙の見解
いいね!
298
【差し有利】ここまで快速馬が揃うGIは見たことがない。初めて京都競馬場で行われるJBC。普段は深い砂の上を一歩一歩踏みしめて、逃げていた馬たちにとって、京都の砂は軽すぎる。気持ちよすぎる。本来だと先行有利の馬場なのだが、みんなで“トリップ”した状態。想像以上のハイペースになると予想したい。
そうなるとマイルで中央GI勝ちのある14モーニンが一気に浮上する。前半無理なくついていって、前がバテた瞬間に狙い打ち。帰国後初戦だが、韓国なんて小倉競馬場に少し遠征したような距離。マイナスにはならない。
3キングズガードの前走1200mは距離不足。今回も同じ距離なら、同様なことが当然言えるが、そのぶん一度使われた後と前では雲泥の違い。しかも、それほど負けなかった。今回は楽しみ。4キタサンミカヅキは中央時代の京都実績が物足りないが、最近の実績を見ると「地方の水が合っていた」だけでは片づけられない成長を感じる。
そうなるとマイルで中央GI勝ちのある14モーニンが一気に浮上する。前半無理なくついていって、前がバテた瞬間に狙い打ち。帰国後初戦だが、韓国なんて小倉競馬場に少し遠征したような距離。マイナスにはならない。
3キングズガードの前走1200mは距離不足。今回も同じ距離なら、同様なことが当然言えるが、そのぶん一度使われた後と前では雲泥の違い。しかも、それほど負けなかった。今回は楽しみ。4キタサンミカヅキは中央時代の京都実績が物足りないが、最近の実績を見ると「地方の水が合っていた」だけでは片づけられない成長を感じる。
元騎手ならではの視点、展開重視 鈴木麻優の予想
鈴木麻優の見解
いいね!
97
競馬記者の決断 鈴木正の予想
鈴木正の見解
いいね!
53
魅せるデータ力 伊吹雅也の予想
伊吹雅也の見解
いいね!
131
平出貴昭の予想
平出貴昭の見解
いいね!
57
最速予想 netkeiba編集部の予想
netkeiba編集部の見解
いいね!
106
※月曜段階の予想ですので回避馬が含まれるケースがございます。あらかじめご了承ください。
ダートの短距離競走としては国内で唯一のJpnIレース。1着賞金も7000万円と高くなく、勝ち馬が種牡馬として評価されることも稀だ。そういった環境から、ダートのスピード馬であっても、強い馬ほどマイルや中距離にチャレンジしていく傾向が強い。その結果として、必然的にこのカテゴリーは限られたスペシャリストたちの争いになる。
1.東京盃組中心
過去10年のうち1400mで行われた5回を除く、1000mか1200mで行われた5回で、連対馬10頭のうち東京盃以外をステップにしていたのは、昨年2着のコパノリッキーだけ。逆に言えば、GI/JpnIを11勝した歴史的名馬コパノリッキーでも東京盃組の壁を打ち破れなかった、ということである。スタートからガンガン飛ばしていくダートの短距離戦は、マイルや中距離とは異質のカテゴリーだ。東京盃は数少ないダート1200mの重要競走であり、レベルの高さは他とは一線を画する。
2.スプリント路線は鮮度が重要
昨年の勝ち馬ニシケンモノノフは6歳馬だったが、1年以内にダート重賞を2勝していた。一昨年の勝ち馬ダノンレジェンドも1年以内に重賞3勝、2015年の勝ち馬コーリンベリーもオープン、重賞を3勝。スプリント戦はひとつのミスや気の緩みが致命傷になりかねない条件だから、集中力や競走意欲がなによりも重要になる。上位には来るものの長く勝ち星から遠ざかっている、というタイプは割り引いて考えたい。
3.上級条件ほど逃げ切りは困難
直線に坂がない京都では阪神以上に逃げ馬有利というイメージがあるかもしれないが、それはおもに下級条件のことである。一昨年以降の集計で、逃げ馬の勝率は500万条件が34.5%、1000万条件が17.9%、準オープンが14.3%、オープン特別が9.1%。ふだん重賞が組まれていないので最上級条件がオープン特別になるが、そこでさえ逃げ馬は苦戦を強いられている。
キタサンミカヅキは昨年夏に南関東に移籍以降11戦5勝。1200mにかぎれば6戦4勝で、交流重賞でも[2-2-0-1]と、中央馬を相手にしても互角に戦えている。以前見られた揉まれ弱さが影を潜め、馬込みで競馬ができるようになったことが躍進につながっている。もともと中央でもオープン特別勝ちのある素質馬が、精神面の成長で本物になった。昨年の当レースも5着とはいえ着差はわずか0.1秒。絶好調で臨む今回は昨年以上の結果を期待できる。
テーオーヘリオスは東京盃では6着に終わったが、休み明けで叩き台という位置づけだったし、初のナイター競馬もあって力を出し切っていない。今春以降6戦3勝で一気にトップクラスに躍進してきた上がり馬で、当コースでは春に天王山Sを勝った実績がある。
グレイスフルリープは東京盃では3着に終わったが、上位3頭のなかでこの馬だけが休み明けだった。前走を叩かれての上積みは少なくなく、ルメール騎手の連続騎乗も心強い。
レッツゴードンキは芝のスプリントGIで2着3回というA級短距離馬で、ダートも苦にしない。追い込み脚質には厳しいコース形態の克服が鍵になる。ネロは詰めの甘さを抱えているが、芝ながら京都では3勝を挙げており、直線が平坦なコース形態はプラスに働きそうだ。
マテラスカイは東京盃を落鉄の影響もあって4着に敗れた。直線が短い京都で巻き返しを期す一戦になるが、芝のスピード馬の参戦が複数あるのが展開的に気になるところだ。モーニンはダートの短距離に矛先を向けて復調の兆しが見られる。レースで集中力に欠ける側面があるので、ここも位置取りがポイントになるだろう。
ダートの短距離競走としては国内で唯一のJpnIレース。1着賞金も7000万円と高くなく、勝ち馬が種牡馬として評価されることも稀だ。そういった環境から、ダートのスピード馬であっても、強い馬ほどマイルや中距離にチャレンジしていく傾向が強い。その結果として、必然的にこのカテゴリーは限られたスペシャリストたちの争いになる。
1.東京盃組中心
過去10年のうち1400mで行われた5回を除く、1000mか1200mで行われた5回で、連対馬10頭のうち東京盃以外をステップにしていたのは、昨年2着のコパノリッキーだけ。逆に言えば、GI/JpnIを11勝した歴史的名馬コパノリッキーでも東京盃組の壁を打ち破れなかった、ということである。スタートからガンガン飛ばしていくダートの短距離戦は、マイルや中距離とは異質のカテゴリーだ。東京盃は数少ないダート1200mの重要競走であり、レベルの高さは他とは一線を画する。
2.スプリント路線は鮮度が重要
昨年の勝ち馬ニシケンモノノフは6歳馬だったが、1年以内にダート重賞を2勝していた。一昨年の勝ち馬ダノンレジェンドも1年以内に重賞3勝、2015年の勝ち馬コーリンベリーもオープン、重賞を3勝。スプリント戦はひとつのミスや気の緩みが致命傷になりかねない条件だから、集中力や競走意欲がなによりも重要になる。上位には来るものの長く勝ち星から遠ざかっている、というタイプは割り引いて考えたい。
3.上級条件ほど逃げ切りは困難
直線に坂がない京都では阪神以上に逃げ馬有利というイメージがあるかもしれないが、それはおもに下級条件のことである。一昨年以降の集計で、逃げ馬の勝率は500万条件が34.5%、1000万条件が17.9%、準オープンが14.3%、オープン特別が9.1%。ふだん重賞が組まれていないので最上級条件がオープン特別になるが、そこでさえ逃げ馬は苦戦を強いられている。
キタサンミカヅキは昨年夏に南関東に移籍以降11戦5勝。1200mにかぎれば6戦4勝で、交流重賞でも[2-2-0-1]と、中央馬を相手にしても互角に戦えている。以前見られた揉まれ弱さが影を潜め、馬込みで競馬ができるようになったことが躍進につながっている。もともと中央でもオープン特別勝ちのある素質馬が、精神面の成長で本物になった。昨年の当レースも5着とはいえ着差はわずか0.1秒。絶好調で臨む今回は昨年以上の結果を期待できる。
テーオーヘリオスは東京盃では6着に終わったが、休み明けで叩き台という位置づけだったし、初のナイター競馬もあって力を出し切っていない。今春以降6戦3勝で一気にトップクラスに躍進してきた上がり馬で、当コースでは春に天王山Sを勝った実績がある。
グレイスフルリープは東京盃では3着に終わったが、上位3頭のなかでこの馬だけが休み明けだった。前走を叩かれての上積みは少なくなく、ルメール騎手の連続騎乗も心強い。
レッツゴードンキは芝のスプリントGIで2着3回というA級短距離馬で、ダートも苦にしない。追い込み脚質には厳しいコース形態の克服が鍵になる。ネロは詰めの甘さを抱えているが、芝ながら京都では3勝を挙げており、直線が平坦なコース形態はプラスに働きそうだ。
マテラスカイは東京盃を落鉄の影響もあって4着に敗れた。直線が短い京都で巻き返しを期す一戦になるが、芝のスピード馬の参戦が複数あるのが展開的に気になるところだ。モーニンはダートの短距離に矛先を向けて復調の兆しが見られる。レースで集中力に欠ける側面があるので、ここも位置取りがポイントになるだろう。
前半3ハロン理論 小林誠の予想
小林誠の見解
いいね!
228
アグレッシブ予想 藤村和彦の予想
藤村和彦の見解
いいね!
400
“絶対数感”の持ち主 大石川大二郎の予想
大石川大二郎の見解
いいね!
1073
元祖“情報” 田沼亨の予想
田沼亨の見解
いいね!
112
厳選予想 ウマい馬券